✔「食事」と「睡眠」の関係性とは?
✔「睡眠の質を高める食事」のメリットは?
✔具体的に「睡眠の質を高める食事」とは?
こんな悩みを解決できます。
現役外科医として
日々健康と向き合っている僕が
しっかりと解説させていただきます。

僕も「食事」への意識を変えることで
今では『食事の重要性』を
再認識することができました。
実際にこの記事で紹介する
『睡眠の質を高める食事』を認識したことで
『質のいい睡眠』を享受する
健康的な生活を送るようになりました。
それにより「日々活力に満ちた」
健康体を手にできました!

結論
『睡眠の質を高める食事のメリット』を享受する
健康的な日常を生活に取り入れるためには
『睡眠の質を高める食事』をする
のたった1つだけです。
記事の前半では
『睡眠の質を高める食事』の具体的なメリット
を解説し
記事の後半では
『睡眠の質を高める食事』のオススメの食材
を具体的に解説します。
食事が睡眠を大きく左右する
「食事」と「睡眠」って一見すると
あまり関係のないように思えますよね。

ですが、食事の内容を見直すだけでも
眠りの質と日中のパフォーマンスを
改善させることができるんです。
つまり
睡眠の質は食事で
大きく変えることができるわけです。
では、食事はどのように
睡眠に関与しているのでしょうか?
さまざまな面で食事と睡眠は
相互に関係しあっているのですが
一番わかりやすいところとしては
覚醒や睡眠に関わるホルモンに
食事からの栄養素が
関係しているということ。

つまり
覚醒や睡眠に関わる物質に
プラスに作用する栄養素を含む食事を
摂ればいいということですね。
では、実際に覚醒や睡眠に関わる
脳内物質をみていきましょう
以下のものがあります。
✔セロトニン
✔メラトニン
✔グルタミン酸
✔GABA
✔アドレナリン
✔ノルアドレナリン
✔ドーパミン
✔アセチルコリン
✔ヒスタミン
✔オレキシン
この中でも最も有名で
最も注目されているのが「メラトニン」です。
やはり睡眠のホルモンと言ったら
「メラトニン」ですよね。
この睡眠に関与する「メラトニン」ですが
食事から摂取できるものではないんです。
食事から摂取する
「トリプトファン」という栄養素が
午前中に受けた光の刺激により
「セロトニン」を産生し
そして夜間になると
「セロトニン」が「メラトニン」に変わることで
体内に増えていくのですね。
このように
睡眠に必要なホルモンをつくる原料や
ホルモンの働きを助ける物質は食事で摂るため
「食事」の内容次第で
「睡眠の質」は大きく左右されるわけですね。

では、睡眠に関係する栄養素としては
どのようなものがあるのでしょうか?
今回は以下のものを取り上げていきますね。
✔トリプトファン
✔ビタミンB6
✔グリシン
✔ビタミンC
✔ビタミンD
✔カリウム
✔カルシウム
✔マグネシウム
✔オメガ3脂肪酸
✔食物繊維
それでは1つずつ見ていきましょう。
トリプトファン
トリプトファンは必須アミノ酸の一種で
催眠や精神安定作用があります。

トリプトファンが不足すると
レム睡眠で乱れが生じてしまいます。
逆に、トリプトファンレベルが改善すると
夜間に目覚めることが減り
起床後の覚醒状態が向上します。
ビタミンB6
ビタミンB6は神経の働きを正常に保ち
催眠、精神安定作用に関わっています。

ビタミンB6はピリドキシンとしても知られ
トリプトファンからセロトニンが産生される工程に
欠かせない物質のひとつでもあります。
ビタミンB群はそれぞれ協力し合って働くので
まんべんなく毎日摂るようにしましょう。
グリシン
グリシンにはノンレム睡眠の質を高め
入眠後の覚醒を減らす
(つまりは中途半端に目を覚ます回数が減る)
効果があります。

ビタミンC
ビタミンCが不足の状態となると
睡眠障害が生じて
全体の睡眠時間が短くなる可能性が
高まってしまいます。
ビタミンD
ビタミンDは概日リズムにかかわる
遺伝子の発現を変えることや
概日リズムと遺伝子を
同期してくれる作用があります。

ビタミンDレベルが上昇することで
日中に眠気を感じることが少なくなります。
また、ビタミンDは
腸内でカルシウムの吸収を助ける
働きもあります。
カリウム
カリウムには睡眠効率の改善
(正しい睡眠サイクルで眠ること)を促し
入眠後に目覚める回数を減らす効果が期待できます。
カルシウム
カルシウムが不足してしまうと
レム睡眠時だけでなくノンレム睡眠時にも
睡眠障害が起こる可能性が高まってしまいます。
また、カルシウムには鎮静効果があるため
不足すると神経過敏になって
不眠を招いてしまいます。
肉類などのタンパク質や
砂糖、塩分などを過剰に摂取すると
カルシウムが消費され
カルシウム不足を招くので注意が必要です。
マグネシウム
マグネシウムには
交感神経系(闘争・逃走反応をつかさどる場所)
の活動を抑制し
副交感神経系(安静と消化をつかさどる場所)
の活動を優位にする力があります。
また、マグネシウムは
抑制性GABAレセプターとの相互作用を通じて
抗不安効果をもたらしてくれます。
このように
マグネシウムはカルシウムとともに
精神の安定に働きます。
カルシウムとマグネシウムの摂取比率は
2-3対1が理想とされています。
マグネシウムレベルを改善すると
睡眠効率が高まり、メラトニンの働きが改善し
コルチゾールレベルが低下し
入眠後に目覚める回数を減らすことができます。
強いストレスや激しいスポーツの後
またはリンを含む加工食品の摂り過ぎは
マグネシウム不足を招きやすいので注意が必要です。
オメガ3脂肪酸
オメガ3脂肪酸の摂取量を増やすと
睡眠が妨害されることが減り
より深く穏やかな睡眠を得られやすくなります。

また、オメガ3脂肪酸
(具体的にはDHAオメガ3)の抗炎症作用により
睡眠時無呼吸の症状が
軽減されることもわかっています。
食物繊維
食物繊維はイヌリンの過剰分泌を防いだり
ビタミンB群の合成に関わり
精神安定に一役買っています。
食物繊維を充分摂っていれば
ビタミンB群の多少の不足は補い
不眠予防の助けになるともいわれています。
睡眠中も脳に働いてもらおう
睡眠への影響を踏まえて
制限したほうがいいものも紹介しておきます。
糖
糖の摂取が増えすぎると
睡眠の質が大幅に低下する恐れがあります。
気をつけましょう。

ですが、適切な糖質は睡眠の質を上げますので
やはりバランスが大事ということです。
アルコール
適量のアルコールは
浅い眠りを誘いますが
深い睡眠の妨げになります。

アルコールが体内に入ると
眠りについた後であっても
レム睡眠の延長や抑圧、もしくはその両方が起こり
脳や身体の機能が
十分に回復されない恐れがあります。
また、アルコールは
「レム睡眠反跳」と呼ばれる現象を
引き起こします。
アルコールの睡眠作用には耐性が生じるため
飲酒を継続していると
睡眠時間は徐々に短縮していき
さらに飲酒を中断すると
かえって寝つきが悪くなり
睡眠は浅くなってしまうわけです。
どうしても飲酒したい場合は
最低でもベッドに入る2-3時間前に
飲み終えているのが理想です。
コーヒー
コーヒーも飲み方で良くも悪くも働きます。

就寝前にコーヒーを飲んでしまうと
カフェインの覚醒作用で
睡眠の質が下がってしまいます。
注意しましょう。
カフェインは神経を興奮させる達人ですからね。
カフェインの持続時間は人によりますが
コーヒーの摂取は遅くても
夕方までにしておいた方が睡眠のためですね。
睡眠の質を改善させるオススメの食材
それぞれの栄養素別に
オススメの食材を挙げていきますね。
是非参考にしてみてください。

トリプトファン
トリプトファンの優れた供給源としましては
鶏肉、ターキー、ロブスター、卵、チーズ
豆腐、高野豆腐、チョコレート、ほうれん草
カボチャのタネ、ピーナッツ、スピルリナ
などが挙げられます。
ビタミンB6
ビタミンB6の優れた供給源としましては
ヨーグルト、サーモン、マグロ、卵
鶏レバー、ヒヨコ豆、にんにく、ほうれん草
カブ、パセリ、唐辛子、アボカド
などが挙げられます。

グリシン
グリシンの優れた供給源としましては
牛肉、鶏肉、ターキー、サーモン、ピーナッツ
キアヌ、スピルリナ、ブラジルナッツ
などが挙げられ
とりわけ骨を煮込んだスープに豊富に含まれます。
ビタミンC
ビタミンCの優れた供給源としましては
カムカムベリー、アムラベリー、アセロラといった
「スーパーフード」に含まれるほか
パプリカ、葉物野菜、ブロッコリー、キウイ
イチゴ、柑橘類、パパイヤなどの
手に入れやすい食品が挙げられます。
ビタミンD
ビタミンDの優れた供給源としましては
サーモン、イワシ、タラ肝油、牡蠣、エビ、卵黄
干し(特に天日干しの)キクラゲ・しいたけ・舞茸
などが挙げられます。
カリウム
カリウムの優れた供給源としましては
アボカド、葉物野菜、サツマイモ
海藻(とくにダルス)、ココナッツパウダー、黒豆
白インゲン豆、ヨーグルト、サバ、サーモン
などが挙げられます。
カルシウム
カルシウムの優れた供給源としましては
ゴマ、チアシード、アーモンド、ヨーグルト
チーズ、豆類、イワシ、コラードグリーン
ケール、ほうれん草、小松菜、モロヘイヤ
大根葉、カブの葉、京菜、ツマミ菜、広島菜
からし菜、野沢菜、春菊
チンゲン菜などの青菜・緑黄色野菜や
ひじき、昆布などの海藻類やキクラゲ
などが挙げられます。
マグネシウム
マグネシウムの優れた供給源としましては
アボカド、カボチャのタネ、アーモンド
ダークチョコレート、葉物野菜、豆腐、納豆、黒豆
脂肪の多い魚、スピルリナ
干しひじき・乾燥ワカメなどの素干しの海藻類
などが挙げられます。
オメガ3脂肪酸
オメガ3脂肪酸の優れた供給源としましては
サーモン、サバ、イワシ、タラ肝油、キャビア
イクラ、牡蠣、藻オイルなどがあげれます。
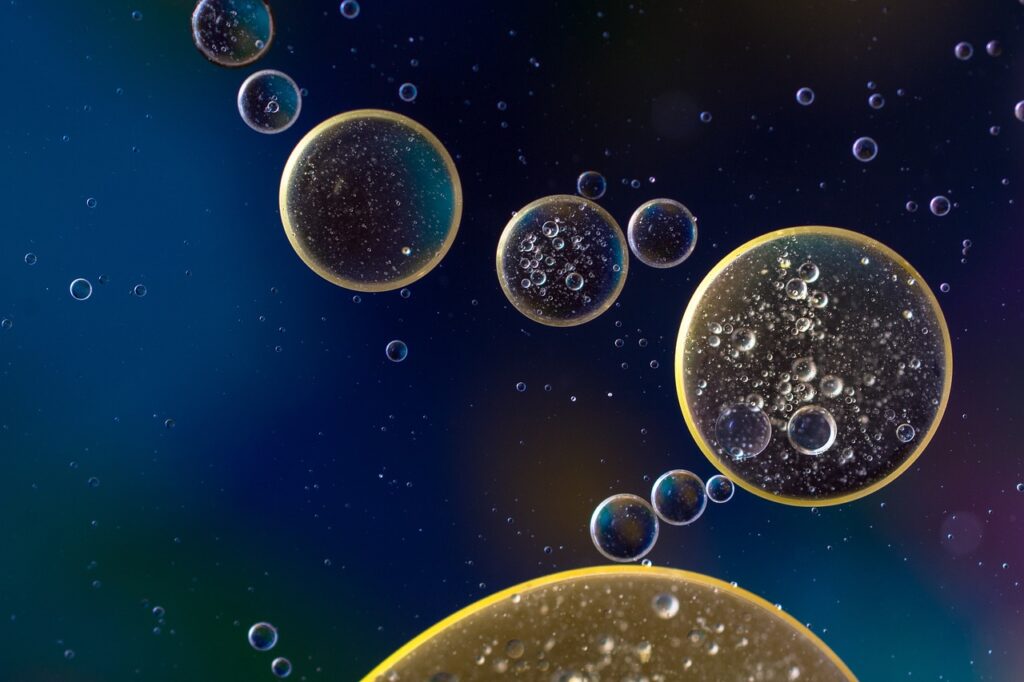
また、植物由来のオメガ3脂肪酸は
チアシード、アマニ、カボチャのタネ
ヘンプシード、クルミに豊富に含まれます。
食物繊維
食物繊維は
植物性食品である海藻類、豆類、野菜類
きのこ類、果実類などに
たくさん含まれています。
まとめ
✔快眠に導く栄養素
[トリプトファン]
トリプトファンレベルが改善すると
夜間の目覚めが減り、起床後の覚醒状態が向上
[ビタミンB6]
トリプトファンからセロトニンが産生される
工程に欠かせない物質のひとつ
[グリシン]
ノンレム睡眠の質を高め
入眠後の覚醒を減らす
(つまりは中途半端に目を覚ます回数が減る)
[ビタミンC]
不足すると、睡眠障害が生じて
全体の睡眠時間が短くなる可能性が
高まってしまう
[ビタミンD]
概日リズムにかかわる
遺伝子の発現を変え
概日リズムと遺伝子を同期
[カリウム]
睡眠効率の改善
(正しい睡眠サイクルで眠る)を促し
入眠後に目覚める回数を減らす
[カルシウム]
不足すると
レム睡眠時だけでなくノンレム睡眠時にも
睡眠障害が起こる可能性が高まる
[マグネシウム]
睡眠効率が高まり、メラトニンの働きが改善し
コルチゾールレベルが低下し
入眠後に目覚める回数を減らす
[オメガ3脂肪酸]
睡眠が妨害されることが減り
より深く穏やかな睡眠を得られやすくなる
[食物繊維]
食物繊維はイヌリンの過剰分泌を防いだり
ビタミンB群の合成に関わり
精神安定に一役買っている
✔睡眠のためには
摂取を制限したほうがいいもの
;・糖
・アルコール
・コーヒー
実践しよう
➀「快眠に導く栄養素」を知る!
➁「睡眠のために摂取を制限すべきもの」
を知る!
➂「睡眠の質を改善させる食材」を
日常生活に取り入れる!
日常生活を大きく変化させることは
なかなか難しいことですよね。
ですので、1つずつでも良いので
日常生活に取り入れてみてください!
是非今日から
一緒に行動していきましょ!
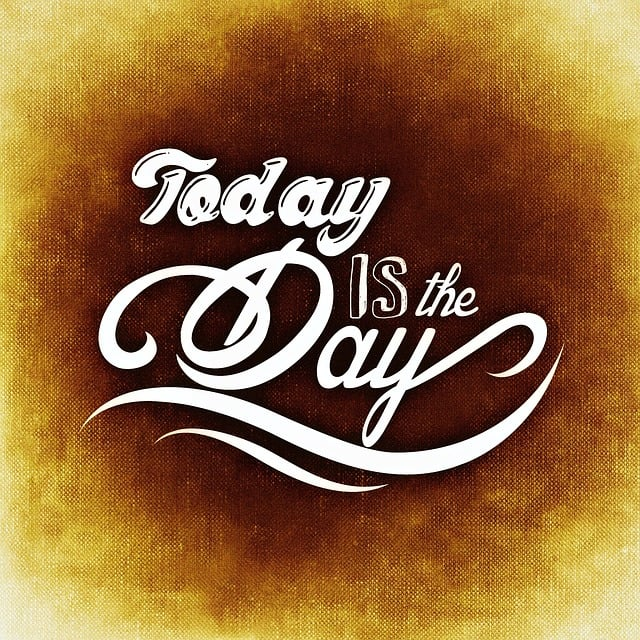
あなたにとって今日が1番若い日!
「先送り」ではなく
「先回り」していきましょう!
そして、健康投資は若ければ若いほど
リターンが大きいもの!
是非、今日から、いや今から
健康に向かって行動していきましょ~
クイズ
知識の復習としてクイズを用意しました。
楽しみながら知識を自分のものとしてくださいね!
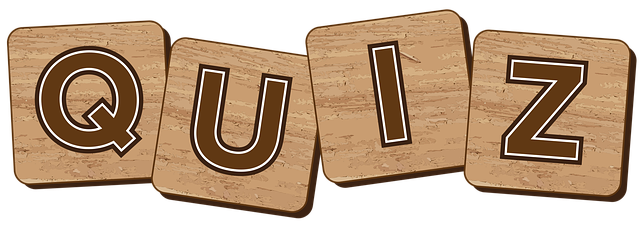
問題
Q1:睡眠の質の向上のために摂取すべき食べ物として
誤っているのは以下のうちどれか。
①ケーキ ②アボカドサラダ ③サーモン丼
Q2:青魚などを食べて
オメガ3脂肪酸を積極的に摂ることは
睡眠にプラスの効果をもたらす。
〇か×か。
Q3:睡眠のためには
摂取を制限したほうがいいものとして
誤っているのは以下のうちどれか。
①アルコール ②タンパク質 ③コーヒー

解答・解説
Q1の正解:①
糖分の過剰摂取は睡眠の質を下げてしまいますで
注意しましょう
Q2の正解:〇
その通りです
オメガ3脂肪酸の摂取量を増やすと
睡眠が妨害されることが減り
より深く穏やかな睡眠を得られやすくなります
Q3の正解:②
タンパク質ではなく、糖ですね
逆に、上記で紹介したタンパク質は
積極的に摂取しましょう
P.S
最後までご覧いただき
ありがとうございます!
私の公式LINEでは
日常生活に寄り添った
予防医学の情報を発信しています。
✅健康で長生きしたい
✅充実した人生を送りたい
✅毎日楽しく生活したい
そんな方にピッタリの情報を発信していきますので
お見逃しなく!
公式LINE登録がまだの人は以下の画像をタップ
👇👇👇
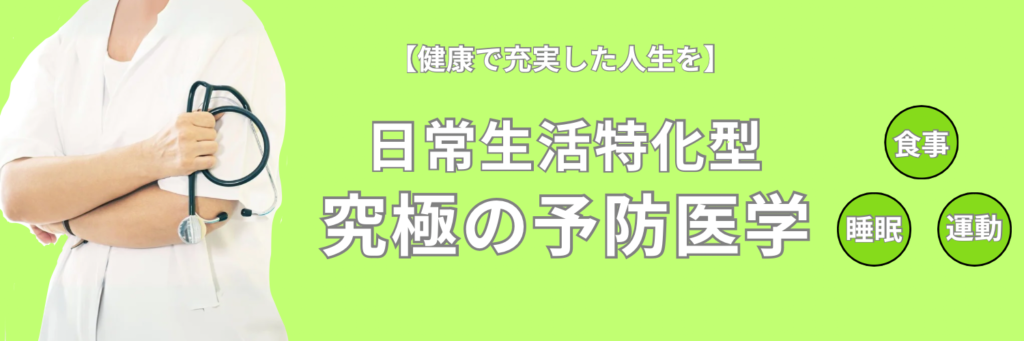


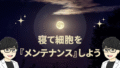
コメント